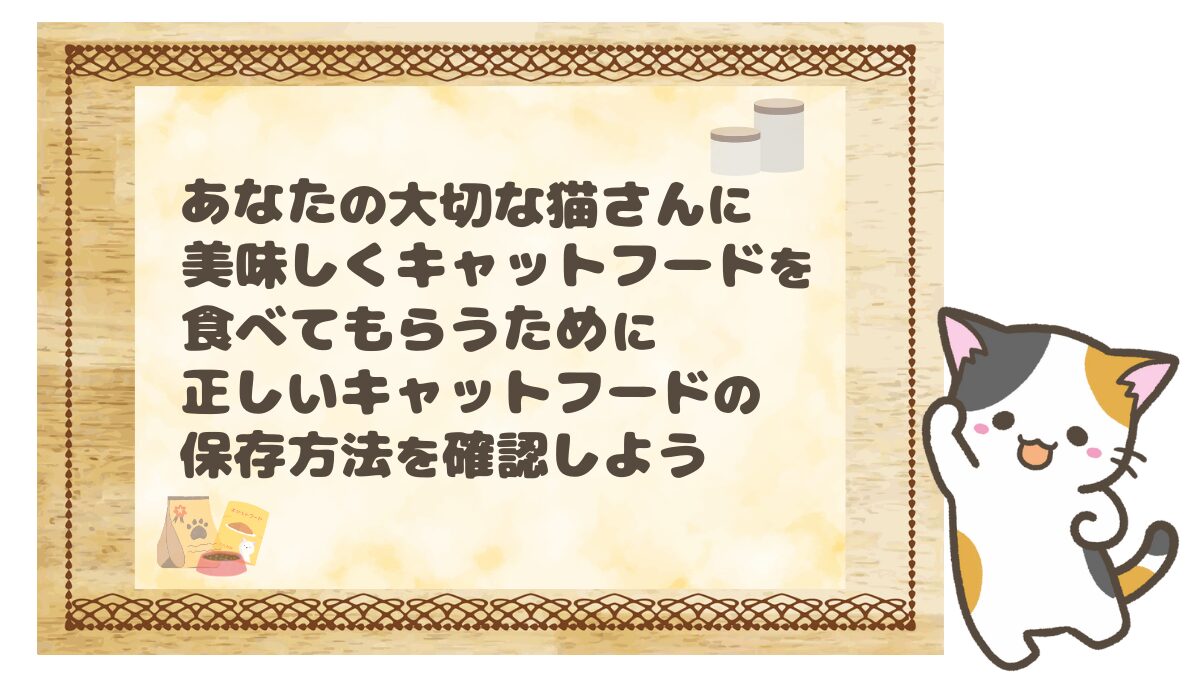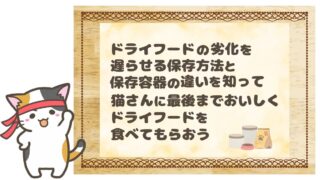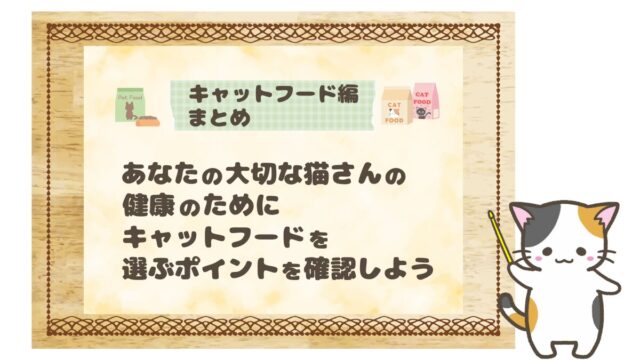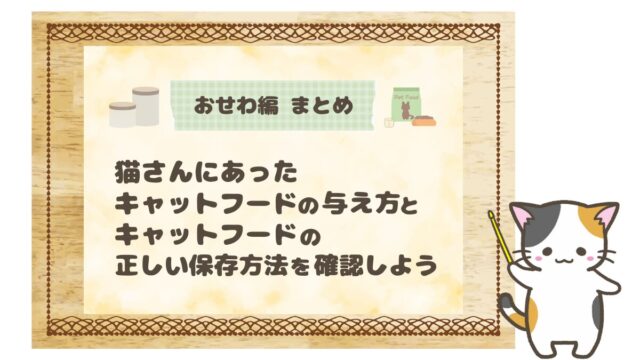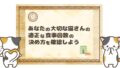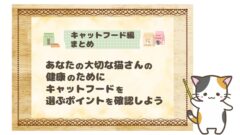ドライフードの保存をしっかりしないと、本来得られる栄養が摂れなかったり、猫さんの体調が悪くなったり、食いつきが悪くなったりします。
猫さんにはしっかり栄養を摂って欲しいですし、最後までおいしくドライフードを食べてもらいたいですよね。
そのためには、正しくドライフードを保存する必要があります。
このブログを最後まで読んで、酸化や劣化を遅らせる保存方法を確認して、しっかりドライフードを保存し、最後までおいしく猫さんにドライフードを食べてもらいましょう。
このブログが、飼い主様と猫さんのお役に立つと幸いです。
ドライフードの保存が大切な理由
ドライフードを正しく保存しないと、ドライフードが酸化して劣化していきます。
ドライフードが酸化したり劣化すると、下記のようになり酸化や劣化が進んだドライフードを猫さんが食べることで、体調が悪くなったり、吐いてしまったり、食いつきが悪くなる場合があります。
そして残念ながらドライフードは、開封した瞬間から酸化や劣化が始まります。
ドライフードの酸化や劣化を止めることはできませんが、酸化や劣化の進行を遅らせることは可能です。
ドライフードの酸化や劣化を遅らせて、猫さんに最後までおいしくドライフード食べてもらうためには、ドライフードを正しく保存することが重要です。
酸化と劣化の違い
ドライフードが劣化する主な原因と保存時に気をつけること
ドライフードは酸化や湿気・時間の経過により、徐々に劣化していきます。
そのため、劣化を遅らせるために、なぜドライフードが劣化していくのか詳しく解説します。
劣化の原因を知り、ドライフードの品質を保持して、猫さんに最後までおいしくドライフードを食べてもらいましょう。
ドライフードの劣化の原因① 湿気の影響
空気中には水分が含まれており、ドライフードが空気中の水分を吸収することで、ドライフードの食感も悪くなり湿気ることで、カビや細菌が繁殖する原因にもなります。
ドライフードの袋に「高温多湿を避けて保存してください」と書かれているのは、このためです。
そのため、ドライフードが空気に触れる回数を減らしましょう。
ドライフードの劣化の原因 ② 時間の経過の影響
正しく保存していても、残念ながら時間が経つにつれて栄養価が低下していき、酸化も徐々に進み、匂いも薄れていきます。
そのためドライフードは開封後、1ヵ月~1ヵ月半を目安に食べきるよう推奨されています。
ドライフードの劣化の原因 ③ 酸化の原因と保存時に気をつけること
酸化は空気・光・温度により進行していきます。
そのため、酸化を遅らせるよう酸化の原因を詳しく解説していきます。
ドライフードの劣化の原因 ③-1 空気(酸素)の影響
ドライフードの袋を開封すると、ドライフードに含まれる脂肪分が空気中の酸素に触れ、酸化が始まります。
そのため、ドライフードの袋は空気が通らない、ガスバリア袋やアルミ袋が使われています。
ドライフードの酸化が進むにつれ、栄養価が低下したり、嫌な臭いが発生したり味も変化するため、ドライフードが空気に触れる回数を減らすことが重要です。
ドライフードの劣化の原因 ③-2 光の影響
太陽の光や蛍光灯などの光が、ドライフードの酸化を加速させる原因の1つです。
そのためドライフードの袋は、光を通しにくい素材で作られています。
ドライフードを保存するときは、光に当たらないように保存しましょう。
ドライフードの劣化の原因 ③-3 温度の影響
熱は、物質の反応を活発にする性質があるため、酸化反応も例外ではありません。
そのため温度が高い場所でドライフードを保管すると、酸化を加速させる原因の1つとなります。
また、ドライフードの袋に「高温多湿を避けて保存してください」と書かれているのは、このためです。
猫さんのドライフードの食いつきが悪くなる原因
猫さんがドライフードの食いつきが悪くなる原因は所説ありますが、食いつきが悪くなる猫さんや、最後の方になると食べなくなる猫さんは、もしかしたらドライフードの酸化や、劣化が原因かもしれません。
なぜなら猫さんは、匂い・味・食感で食べ物を選んでいるため、酸化や劣化により匂いが薄くなったり・嫌な臭いを感じていたり・味や食感が開封したての時と変わっているなどで、ドライフードの食いつきが悪くなったり、最後の方は食べなくなってしまうのかもしれません。
また、猫さんは本能的に自分に必要な栄養を感じ取り、ごはんを選んでいると聞いたこともあります。そのため、開封時よりも栄養価が低下したフードに、食欲が湧かない可能性も考えられます。
人間も無意識に食べたいもので、必要としている栄養が分かるように、感覚の鋭い猫さんが栄養価の低下を感じ取っていることは、あながち間違っていないのではないでしょうか。
ドライフードの食いつきが悪くなる猫さんや、最後の方になると食べなくなる猫さんは、ドライフードの保存方法を見直すことをオススメします。
ドライフードの保存方法で気をつけること
開封後のドライフードを保存する際に気をつけることは、「保管場所」・「保存容器」・「大袋のキャットフードで小分けにされていないならば、小分けにして保存する」の3つが重要です。
この重要な3つについて、詳しく解説していきます。
ドライフードの保管場所はきちんと選ぼう
未開封や開封後のドライフードは、「直射日光が当たらず、高温多湿にならない場所(キッチンの棚・パントリー・床下収納など)」が最適です。
シンク下に保管していることが多いと思いますが、シンク下は水を使っているため、湿度が思った以上に高く、ドライフードを保管するには適していないので注意しましょう。
ドライフードを保存容器に入れて保存する必要性
開封後のドライフードをクリップなどで留めて、保存している方が多いのではないでしょうか。
猫さんにおいしく最後まで食べて欲しいのであれば、開封後はクリップで留めて真空容器にいれて保存することをオススメします。
なぜならクリップでは密封できないため、空気が入ってしまっているからです。
また、ジップ付きのドライフードを袋だけの保存も、あまりオススメはしません。
なぜならジップ付きの袋は、ジップ部分にドライフードの細かい破片が付着していてキチンと閉まっていなかったり、ジップの閉じ損じが生じてしまうことがあるからです。
もしも袋の口が閉まっていなかったとしても、真空容器に入れておけば、ドライフードの袋の中に空気が入ることが防止できます。
保存容器には種類があるので違いを理解して選ぼう
ドライフードの小分け保存
大袋のドライフードのままだと、猫さんにごはんを与えるたびに袋を開封するため、ドライフードが空気に触れる回数が増え、ドライフードの酸化が促進されてしまいます。
ドライフードを小分けにしておけば、ドライフードが空気に触れる回数が減るため、ドライフードの酸化を遅らせることができます。
小分け保存する際には、真空容器や真空パックにして保存しておくとより、ドライフードの鮮度が保てるのでオススメです。
ウェットフードの保存方法
ウェットフードは気密性の高い容器を使い、レトルト殺菌されて作られているため、保存料が使われていません。
そのため開封後は傷みやすいので、使いきれなければ必ず冷蔵保存しましょう。
なお、冷蔵保存でも1日~2日以内には使いきりましょう。
ドライフードの間違った保存方法
普通の袋でジップ付きのものを、ドライフードの小分けに使われていたり、ドライフードを冷蔵・冷凍保存している方もいるようですが、それはあまりオススメしません。
それぞれのオススメしない理由を詳しく解説していきます。
ドライフードのジップ付き袋での保存
ジップロックなどの、普通の袋にジップ付きのものは、ドライフードの小分けには適していません。
なぜなら普通の袋は空気が通過できるようになっているため、密封できておらず、なおかつずっと空気に触れたままになっているからです。
空気を通さない専用の「ガスバリア袋」や「アルミ袋」でなければ、空気を通してしまいます。
そのためドライフードを小分け保存するならば、ガスバリア袋を使い真空パックにして、保存することをオススメします。
ドライフードの冷凍・冷蔵保存について
ドライフードを冷蔵・冷凍保存についてよく見ますが、オススメはしません。
なぜなら冷蔵・冷凍保存して冷たくなったドライフードは、ドライフードの匂いが薄くなります。
また、常温で解凍をおすすめしていることを見たことがありますが、冷たいドライフードは湿気を吸いやすくなるため食感が悪くなります。なお、レンジで温めるとドライフード本来のカリカリ感が損なわれるため、こちらもオススメしません。
猫さんのことを考えるなら、ドライフードの冷凍・冷蔵保存はしないほうがよいでしょう。

お読みいただき、ありがとうございました。
このブログがお役に立てば幸いです。
覚えておきたい基礎知識